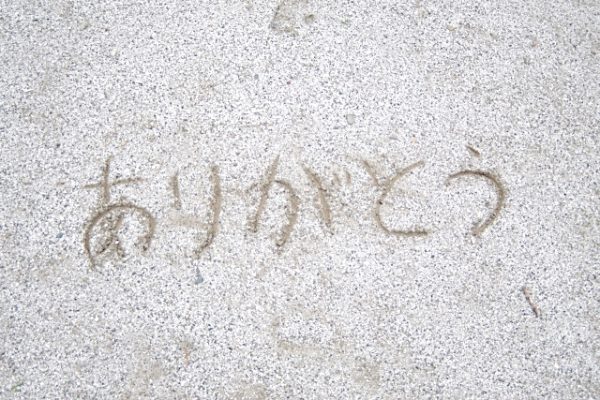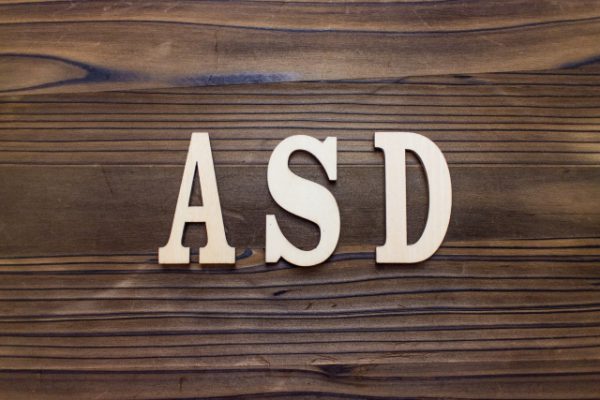メンタル・イデア・ラボの本城ハルです。
私は現在進行形で発達障害重複を持つ思春期真っ盛りの、面倒くさい息子を養育するシングルマザーです。
修羅場の峠は越えたように思いますが、定型と言われる子供を養育している親に比べると、やはりぶつかり合いは多いのではないかと思います。
WAISで言語は高い息子。でも、特性による認知の歪みから他者間コミュニケーションにズレを生じやすく、また障害特性ゆえに行動に親はモヤモヤイライラしてしまうのが日常です。
さすがにもう血の雨は降りませんが(笑)、減ったとはいえ言い合いになるにもこれまた日常でです。そんな時、息子は自分の部屋に私はリビングで物理的距離を取り、クールダウンします。その後は必ず「さっきは嫌な言い方をしてごめん」「私こそキツイ言い方してごめんね」「実は学校で嫌なことがあって・・・」という流れです。
思春期真っ盛りのこの時期は親に反発しまくる反面、甘えたいというアンビバレント(相反する感情などを持ち葛藤する)な時期でもあります。「母さんの言うことは正論過ぎてムカつく」と言われたことがあります(笑)可愛いさと悪魔が同居していて「ツンデレか!?」と思う毎日ですが、ふと「あー、大人の階段を上ってる最中だもんね」と思ったり。
多少落ち着いたとはいえ、壮絶な親子バトルを繰り広げていた過去を持つ我が家ですが、今の私と息子の関係はかなり良好と言えます。言い合いになる時はあっても、ほとんどは落ち着いて話ができるようになりました。時々ヘンなテンションになり、いきなりタコ踊りを披露してくれる息子に対抗して、私も息子が「お、おう・・・(汗)」な反応をするような返しをしますし、買い物には嫌がらずに荷物持ちとして同行してくれます。外食にもホイホイついて来ます。
何より、「何か困ったことがあれば、かーちゃんはちゃんと話を聞いてくれる、力になってくれる」と思ってくれているようです。ありがたいですね。
その信頼関係のベースにあるものは何なのか?を考えた時に、小さなことでも家庭内に「ありがとう」が当たり前にあること、ちょっと時間はかかっても(クールダウンする)、お互いに「ごめんね」がこれまた当たり前にあることもあるのではないかと思いました。
家族だから言わなくてもわかってくれるはず←家族は血の繋がっただけの(夫婦なんて血も繋がっていない他者)他者ですし、そもそも自分以外、世界中の人は皆他者なのですから「言わなくてもわかる」なんてあり得ません。自分以外、エスパーならわかるかもしれませんが(笑)「言わなくてもわかってくれる」なんて、傲慢以外の何ものでもありません。
家族にいちいちお礼や謝罪なんて照れくさい←恋人に面と向かって「愛してる」と伝えるわけでもないのに、何だか照れくさいの使い方は間違ってますし、大人としてはイマイチカッコ悪い考えに思えます。歳を重ねたよい大人だからこそ、他者の小さな好意や厚意に対し、意識的に「ありがとう」「すみません(ごめんね)」が言えるのではないでしょうか。
「ありがとう」も「ごめんね」も人間関係を柔らかく、他者の気持ちも柔らかくする言葉です。
これからもパートナーに、子供に、友人に。もちろん親に対しても素直に言える自分でありたいと改めて思いました。
◇
<運営会社:Jiyuuku Inc.>