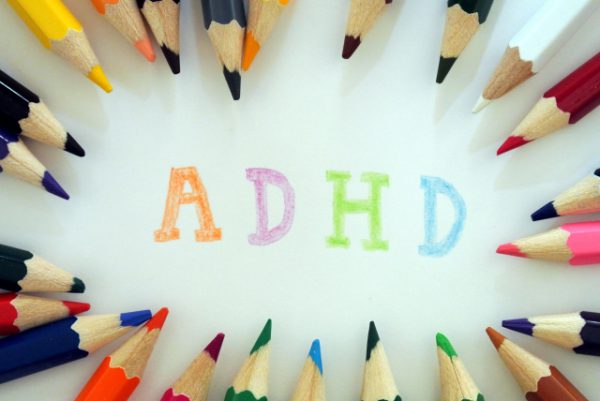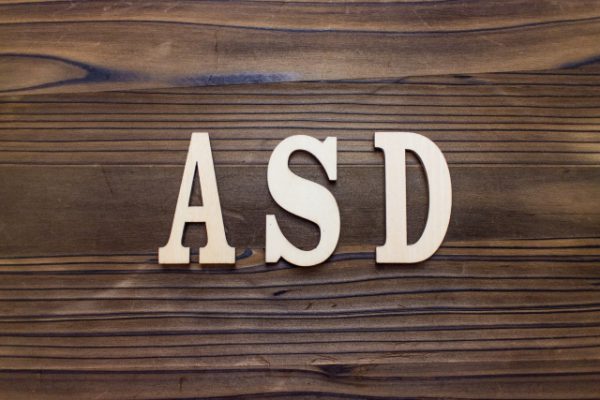⚠︎:発達障害は先天的な脳の発達の偏りなので、親の躾や環境、また、本人のせいでもありません。発達障害をややこしくしているのは、無理解、無知からくる不適切な対応などでさまざまな神経症や精神疾患を併発したことによる二次障害といえます。
メンタル・イデア・ラボの本城ハルです。
前回からの続きで、私が感じる特性(特徴)とパートナーに聞き取りをしながら書いている【2】になります。それでは実像に迫ってみましょう。
『ASD孤立型重複なし』はASD三つ組の特性の中でも、特に人間関係の考え方や築き方に特徴があるようです。
基本はASDなので特性に濃淡はあっても強いこだわりやマイルールは当然ありますし(私は気にしておらず、そのこだわりを尊重しています)、自分のペースを乱されたり先の見通しが立たないことや、いきなりの予定変更には私たちが考えられないくらいの強いストレスを感じるそうです。例えば、今日からこうしてください、今日からこうします、と言われた時、表面上は了解し従うものの、内心では拒絶反応があるようです。つまり、拒絶しながらも従っている、という矛盾を抱えた状態になるようです。表面上はまったくわかりませんね。
またネガティブな感情や気持ちを整理したり、折り合いをつけるにも結構時間がかかります。『寝たら忘れる』などお気楽さはないようで、パートナー自身の問題として時間という薬が必要です。長い時は1週間から2週間かかるそうです。その間、折り合いをつける過程で、内心で起きているのは自暴自棄であり、絶望であり、怒りであり、負のスパイラルに陥って極論まで含めた相当な葛藤があるようです。
そのような時は少し話すとわかるので、そっと見守るという放置タイムになります。ここで「何で?」「どうかした?」「どうしたの?」を繰り出すと、あまりのウザさに心のシャッターをピシャリと閉め“閉店”あるいは“閉鎖”、下手をすると強制終了(別れる)になる可能性大です。
普段からこっちに来るなオーラが無意識に出まくってしまうのと、見た目も怖いので(人当たりは抜群に悪い)、人混みを歩いていると自然とパートナーの前には道が開け、誰にもぶつからずに早足で歩いています(まるで海を割るモーゼの十戒のような?)。歩きやすくて羨ましい限りですが、一緒にいる私はなぜかガンガンぶつかられます。一緒に歩いていても、その恩恵は受けられません・・・残念です(泣)
◇
「友人はいない」「いらない」と言い切っていますが、一緒に食事を楽しむ“知り合い以上友人未満”のような人はいるようで、孤立型で他者に無関心ではあるものの、人嫌いという訳ではなく引きこもりでもないので、お酒も飲む彼は歓楽街へ飲みにも行きます。ただし必ず決まって一人で行きます。誰かを誘って飲みに行こうとは決して思わないそうです。
行動“だけ”を見れば、とてもASD孤立型には思えませんが、やはりそこは孤立型、「たまには誰かと食事へ行くし、ホステスさんがいるお店に飲みにも行くけど、いつも内心は『独り』の感覚」だそう。
それはどういうことか尋ねたところ、
「物理的には一緒に飲み食いしながら何かしら話しているけど、精神的には一緒にいる感覚はない。分離している感じ。交流しているようで実はしていない感じ」
よくわからないので、さらに説明を求めたところ、
「例えとしてどうかわからないけど、同じコップに入っている水と油みたいなイメージ。そもそも同じコップに入りたくないのが基本スタンスだから、同じコップ(一緒に飲み食いしている)に入っている時点で自分としては十分なんだよね。だから入っているからといって、わざわざ混ざり合うことはないかな、と。相手が水でオレが油だとしたら、水と油は決して混ざり合わないで分離するでしょ?話が合わないという意味では決してなくて、それなりに楽しいんだけど、たぶん共感という界面活性剤がない状態だから、感情の部分で交流できていないんだろうね。水と油が入った瓶を振ると混ざったようになるけど、振るのを止めたらすぐ分離するでしょ、あんな感じ。会話している時は瓶を振っている時と思ってもらうといいかも。ドレッシングなコミュニケーションだな(笑)」
独特な例えだなと思いながら、なるほど共感力が乏しい故に内心では独り、と感じるのは頷けます。だからといって、孤独感に陥って落ち込んだり寂しくならないのは、孤立型特有の『他者に興味・関心がほぼないことが基本スタンスであり、そもそも一人がいい』という特性の成せる技なのだろうと思われます。
私はつまらないほど定型なので、仲のよい友人とはくだらないやり取りをしょっちゅうしていますし、バウンダリーも当然近いと思っています。そのため間違いなく互いに友人と認識し、存在に感謝し合っている(だろう)と思っていて、その感覚とパートナーのそれはまったく違うものに感じます。
パートナーの場合、私のように互いに友人と認識し、存在に感謝し合う関係になるまで、相当な時間を要するだろうと想像します。いや、最初からそんな関係は望んでいないかもしれません。会うのは年に2〜3回、連絡は会う際の段取りを決める時だけ、会っても交流しているようで実はしていないとなれば、私が私の友人達に対して思っている感覚に至るのは、現実的には正直難しいだろうなと思います(笑)下手をすれば自然消滅することが濃厚です。
その点をあえて聞いたところ、
「自然消滅した人?、うーん、自然消滅したかどうかわからないけど、長いこと連絡を取り合っていない人は何人かいるよ。」・・・やはり(笑)
さらに、もしそういう人から久しぶりに連絡があったらどうするの?と聞くと、
「普通に話すし、会おうとなれば会うよ。別に嫌いな人じゃないから。」
逆にずっと連絡がなかったら?と聞くと、
「それはそれで構わない。だいたい自然消滅はお互い確認のしようがないから、個々人の時間軸で計って、自然消滅したと思ったほうが勝手にピリオドを打つんだよ。」
でした。パートナーの中では自然消滅している感覚はないようで、たまたま長い間会っていないだけ、に過ぎないようです。仮に自然消滅していたとしても構わないと言い切ってしまうあたり、まるで一期一会のような人間関係の構築ですね(笑)
◇
<運営会社:Jiyuuku Inc.>